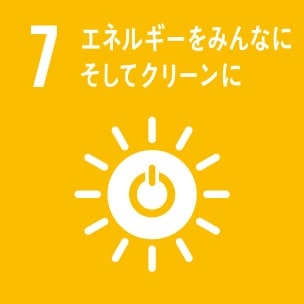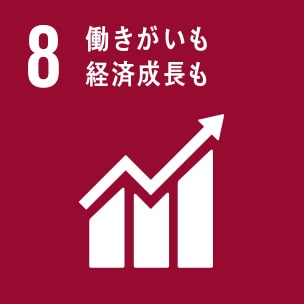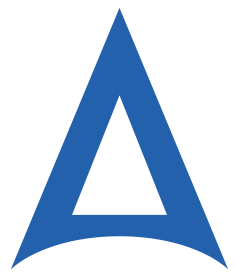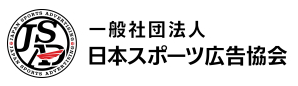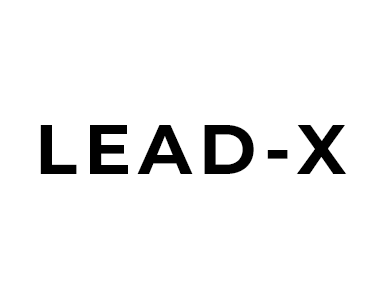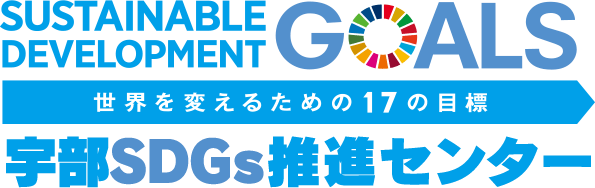損害保険ジャパン株式会社 山口支店 宇部支社
損保ジャパンでは、社員ひとりひとりがSDGsの理解を深め行動につなげる取組として「#SDGsみんなでアクション」を展開し、SDGsや社会貢献活動に関連する取組を社内で共有しあう活動を行っています。
また当社は全国に拠点を有する損害保険会社として社会的責任を果たし、SOMPOグループの持つノウハウを活かして地域とともに成長すべく、地方創生への貢献に取り組んでいます。これまで自治体様と締結した協定数は294件(2024年3月末)にのぼり、協定の分野は、防災・減災、産業振興、観光振興、交通安全、シニア・介護・ヘルスケア等、多岐にわたっています。
【取組例】
・SAVE JAPAN プロジェクトと呼ばれる、NPOと地域の皆さまと、損保ジャパンが一緒になって、全国各地で「いきものが住みやすい環境づくり」を実行するプロジェクトを行っています。
・全国の新小学一年生の交通安全を願って交通事故傷害保険付きの「黄色いワッペン」を贈呈しています。
・将来を担う子どもたちとその保護者を対象に、災害から身を守るための知識や安全な行動を身に付けてもらうことを目的としたプロジェクト「防災ジャパンダプロジェクト」を全国各地で開催しています。
・山口支店独自の取組として、保険代理店の皆様と連携し、フードバンクへの寄贈や、使用済みコンタクトレンズケースの回収等を行っています。
・SDGsが目指す世界への道のりや当社のSDGsに関する取組みをゲーム形式で体感することで、SDGsの理解を深め、行動につなげるための当社オリジナルコンテンツ「The Action!~SDGsカードゲーム~」のご用意もあります。
・地震保険・自賠責保険の普及・啓発